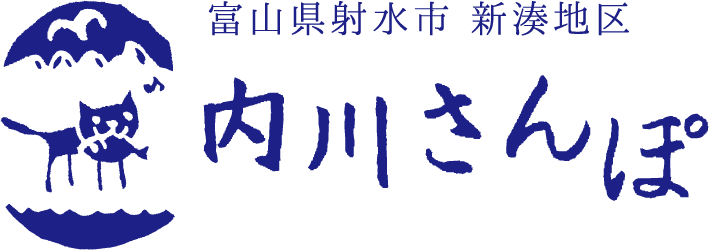毎年10月1日、13本の曳山が、昼は「花山」、夜は「提灯山」にしつらえられ、町中を練りまわる。
内川が流れる新湊地区のお祭りとして、人々がまず口にするのが、毎年10月1日に行われる「曳山まつり」です。ぎゅっと密集した家々の建ち並ぶ狭い道を、豪華な曳山が連なって進む華やかさと角切りの家の角をギリギリで曲がる勇壮さ、それを曳く男衆の威勢の良さは住民たちの誇り。心躍るお囃子の音が、まち全体を興奮で包む日です。
「この1 日があるから、後の364日なんとか生きられる」と豪語する祭り好きも多数。大切なまっつん(=祭り)の日、もちろん仕事は休み。この日に合わせて帰省する転出者も多く、観覧客はもちろん、住民や元住民が急増する日でもあります。
曳山祭りは、もともと放生津八幡宮の秋季大祭の一部。海から来られた神様を境内の老松のもとに招き入れて行われる10 月2 日の「築山祭」が本祭です。神様の姿を人形で表現し、氏子たちのために町内を巡れるよう曳きまわす形になったそう。人形や装飾は時代を反映したアレンジを加えながら、今に引き継がれています。
そして、春は獅子舞。五穀豊穣や大漁満足などを、各地区の氏神様にお祈りした後、地域の獅子方が家々を巡ります。
愛嬌たっぷりの顔でゆさゆさと舞う獅子と、色鮮やかな衣装で舞う子どもや若衆たち、心地よく響くお囃子の音…。獅子舞の日は、まち全体が浮き足立ち、喜びに包まれる日。獅子舞のある地区が密集しており、祭礼の日も重なっているため、いくつもの幸せな光景に出会えます。

- 1・2┃ 放生津八幡宮の秋季大祭は9月30 日の宵祭りから10月3日までの4日間行われる。13本の曳山は、10月1日の「神輿渡御」のお供として曳かれる。「花山」も「提灯山」も、狭い街角を民家スレスレで曲がるのが見どころのひとつでもある。
- 3・4┃各町内の獅子方による獅子舞。東西2kmの内川界隈に、20あまりの獅子舞が密集しており、遭遇率が高い。
- 5┃お祭りの日、多くの漁船には大漁旗がなびく。
- 6┃50 年ほど前から、夜になると松明を持って舞うのが一帯に定着し、夜はさらに見ごたえが増す。
- 7┃お祭りの約1 か月前から踊りやお囃子の練習が始まる。夜、まちに響く笛や太鼓の音は情緒満点。