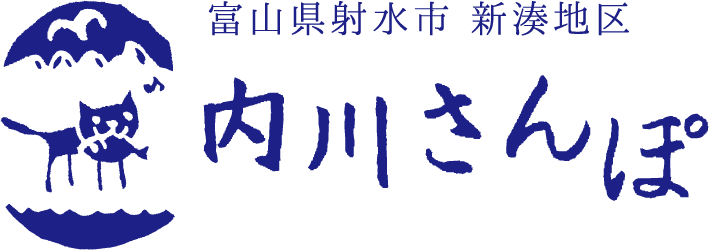漁に出かける際、舟の上からお参りできるよう、海側を向いている。
内川界隈を歩いて驚くのは、「おんぞはん」と呼ばれるお地蔵さまのお堂の多さと立派さ。この界隈に150カ所もあると言われているだけあって、辻々で出会えます。「人通りの少ない道ばたにお地蔵さま」という光景は、全国各地で目にしますが、内川の「おんぞはん」たちは、しっかりと人々の暮らしにとけ込んでいます。どの「おんぞはん」も、ちゃんと“毎日営業している”というか、何人もがお世話やお参りにやって来て、大切にされていることが伝わってきます。
海で生計を立てていた人が多い内川界隈。「板子一枚下は地獄」ということわざがあるように、海での仕事は死と背中合わせでした。人々は海上での無事と大漁を祈願して、様々な神仏をまつり、恵みをもたらしてくれる海や自然に、感謝と畏敬の念を表し続けてきました。また、海岸に沿って発達してきた町は、浜風によって大火になりやすかったため、火伏せに対する信仰の厚い地域でもあります。
そして、内川の周辺には歴史ある寺社が密集しています。古くは平安や鎌倉の時代に創始されたものもありますが、多くは江戸~明治にかけての創立・創建。今でも、内川にかかる橋の先がそのままお寺の参道につながっていたり、主要な道の辿り着く先に神社があったりします。内川周辺は、神社や寺院を中心にまちが形づくられている門前町のような雰囲気を持っているのです。

- 1┃ 光明寺前の「おんぞはん」。この界隈の地蔵堂は、暗くなるとちゃんと電気がつき、賑やか。
- 2┃毎朝のお世話や掃除は、ご近所どうしで担当を決め、交代で行う。
- 3┃「お参りがおわったら、木の扉を閉めておいて下さい。寒い時期なので…。」と張り紙が。おんぞはんは、温かそうな手編みのケープを羽織っていた。
- 4┃漁師の信仰を集める「魚取社」。この界隈は漁の神様=恵比須様を祀る神社が多い。
- 5┃ 区画整理のため、一時的に駐車場に置かれていた地蔵堂。
- 6┃鮮やかな色のおりん台。お経のビーズ刺繍が。
- 7┃少子高齢化によるお世話の負担を減らすため、おんぞはん26 体を合祀し2017年に新設された「奈呉町地蔵尊」。