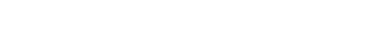エリア01
海王丸~新港大橋

音声ガイド(約15分)
音声ダウンロード以下の音声が流れます
海王丸
進行方向左側に見える帆船は、海の貴婦人と呼ばれる「海王丸」です。
海王丸は商船学校の練習船として、現在横浜に係留されている「日本丸」とともに誕生した帆船で、昭和5年1930年2月14日に進水、平成元年1989年9月16日に退役するまでに106万海里、地球約50周を航海し、11,190名もの海の若人を育てた帆船を現役の姿のまま公開しています。
進水日がバレンタインデーであることや、海王丸パークが県内有数のデートスポットでもあることから、「恋人の聖地」に選定され、これを機に船上で「幸せのベル結婚式」が実施されています。
「日本の海の王者にふさわしい船にしたい」と「日本丸」「海王丸」と命名されました。白い帆を張った姿がうつくしいことから美しい姉妹にも例えられており、ボランティアにより29枚ある帆をすべて広げる総帆展帆が4月から10月まで、年間約10回行なわれています。
新湊大橋
前方に港の入り口に架かる橋「新湊大橋」が見えます。港が開港する前は、小さな橋と鉄道の鉄橋で繋がっていましたが、富山新港の建設に伴い昭和42年1967年11月に港口部が切断されました。開港に伴いフェリーボートが就航し迂回道路がつくられましたが、後に、人々の生活や産業、経済活動などに重大な影響が出始めたため、平成14年2002年秋に大橋の建設が本格着工され、およそ10年の歳月をかけ平成24年2012年9月に開通、45年ぶりに分断された東西の地区が繋がりました。
新湊大橋の総延長はアプローチ部分も含めておよそ3600m、水面からの高さは47メートル、総事業費485億円を投じた日本海側最大の斜張橋です。この橋は上が車道、下は歩行者通路の2層構造になっており、東西のエレベーターから空中散歩を楽しむことができます。
晴れた日には、橋から日本海や立山連峰、能登半島が一望でき、青空と白い橋のコントラストとともに絶景を堪能できます。
富山新港
それではこれより富山新港に入ります。この地域は、古くから射水の名で呼ばれていました。奈良時代の746年の頃、大伴家持が越中の国司に赴任した5年間、この地方の風物を詠んだ歌の多くが万葉集に収録されています。
「みなと風 寒く吹くらし 奈呉の江に 妻呼び交わし 鶴さはに鳴く」
河口の風が寒々と吹いているらしい。奈呉の江で、夫婦で呼び合いながら、鶴がたくさん鳴いている。
当時の国府の館は二上山の東にあり、そこから眺めた海を奈呉の海、浜辺を奈呉の浦、潟を奈呉の江と呼んでいました。今でも奈呉の江は地名に残っています。鎌倉に幕府ができると越中の守護所は奈呉の江のほとりに設けられ、その館はのちに放生津城と呼ばれ、地名も放生津と改められました。中世において放生津城は北陸の名城であったと今に伝えられています。
かつてこの富山新港は、放生津潟という天然の池であり、東西2.4km、南北1km、面積1.8平方キロメートルの大きさで最も深いところで1.5mと、浅い半淡水湖でした。淡水魚ではフナ、コイ、ナマヅ、雷魚などが、生息し、後に汽水魚のうなぎや、ぼら、しじみ類をたくさん繁殖していました。
富山新港はこの放生津潟を利用した掘込港湾で新産業都市建設の一環で7年の歳月を費やし昭和43年1968年に開港しました。
同時期に浚渫土砂を利用して形成された背後の工場地は金属、機械、木材関連産業等の企業が集積し、工業港湾として発展、国際拠点港湾に指定されています。
新港大橋
新港大橋が見えてきました。
高岡市と射水市を結び、海王丸パークへの連結道路に接続しています。
新港大橋は市発展のシンボル「海と貿易」をテーマとして構成されています。4本の親柱には、波に浮かぶ地球がデザインされており、国際拠点港湾のシンボルとなっています。
内川
これより内川に入りますが、内川には万葉線の電車が走る鉄橋を含めて11の橋がかかっています。
内川は庄川河口と、放生津潟、現在の富山新港を結ぶ2級河川です。
富山新港に通じる放生津口を境に、東内川1.85kmと西内川0.45kmに分けられます。
その昔放生津潟は、東内川によって富山湾と結ばれていて、船が行きかう運河として、役目を果たしていました。
射水平野の農村からの、物資は周辺の湿地帯を流れる多くの川をへて、さらに内川を通って、各地へと送られていました。内川は中世において栄えた放生津港につながる運河として、単なる排水路ではなく、人々の生活に深い関わりを持った川としてその役割を果たしてきたのです。